インタビュー・文/池田敏明
写真/小林浩一
スポーツ先進国であるアメリカで、最も人気のある競技として知られるアメリカンフットボール。高度な情報分析と複雑な戦術を駆使しながら、高い身体能力を備えた屈強な男たちが戦うアメフトの最高峰NFL。目の肥えたスポーツファンを虜にし、その優勝決定戦であるスーパーボウルは国民の半分がテレビ視聴すると言われるほど注目度が高く、それゆえに放映権料やスポンサー契約料などで莫大な金が動く。
そんなNFLが、1990年代後半に日本への進出を目指し、オフィスを構えたのを皆さんはご存知だろうか。そのプロジェクトにおいて中心的な役割を担い、日本で設立されたNFL JAPAN Link 代表、そしてNFL JAPAN 株式会社 社長を長年に渡って務めたのが、町田光氏だ。
町田氏はアメフトはおろか、本格的なスポーツ競技経験はゼロ。スポーツビジネスに関しても全くの門外漢だった。しかしアメフトの日本普及と人気拡大についてしたためたレポートが好評を得て責任者に抜擢され、日本での市場開拓に向けて奔走した。
そして、その手腕が評価され、現在はJリーグマーケティング委員としても活動している。草創期こそ大ブームを巻き起こしたJリーグだが、近年は観客動員が落ち込み、地上波での放送もほぼなくなるなど、苦闘の中にある。その理由はどこにあるのか。そして、今後どのような方向を目指せばいいのか。日本のスポーツビジネス界の「トリックスター」を自称する町田氏が、その極意を楽しく語る。
「スポーツファン」について考える 顧客を知ることから始まる
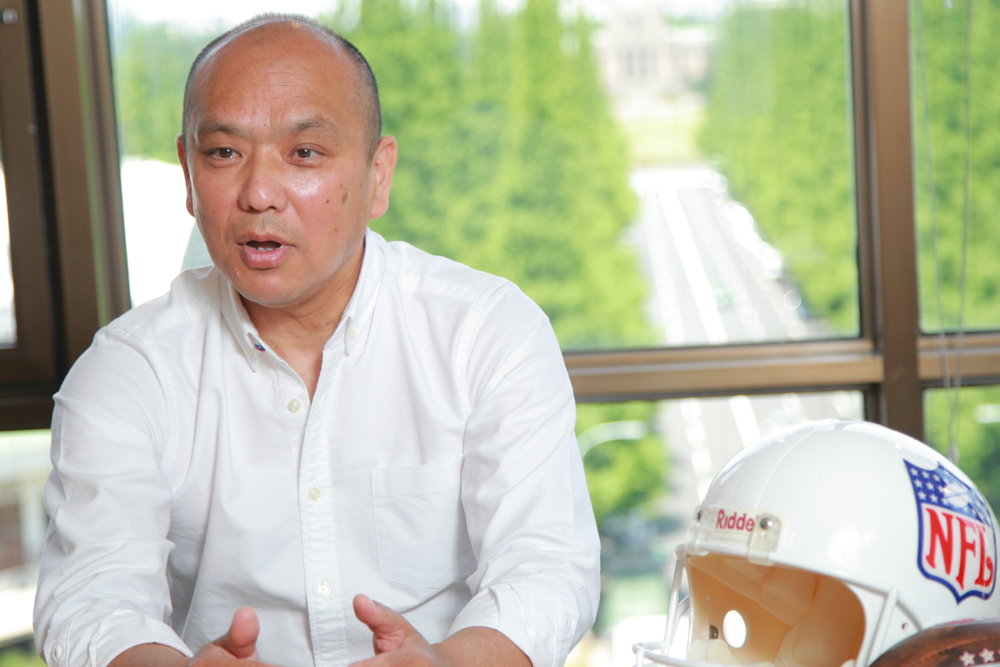
――世界最高の売り上げを誇るNFLは、他のスポーツリーグ運営と比較してどこが優れているのでしょうか。
町田 光 ビジネスの原則に忠実で、それを徹底してやるところですね。ビジネスは「顧客の課題の解決」なんです。NFLは現代社会の在り様や、そこに生きる人々の心理や欲望を見つめ、そこにどんな課題があるのかを探り、NFLとそのチームはどんな課題を解決する価値を人々に提供できるか、ということをいつも考えています。最高品質のアメフトの試合が全ての基盤ですが、その上に人々との間に共有できる様々な物語を構築して、多くの人に理解される言葉やイメージとして伝えていくということを、極めてちゃんとやっている。だからこそアメリカにおいて圧倒的に人気があるんです。僕がNFL Japan LINKを立ち上げたのは1996年ですが、当時アメリカでは「NFLはもうピークで、これ以上の伸びしろはない」と言われていたんですよ。NFLの内部ですらそうでした。だから国際化に乗り出して、マーケットを開拓しようとしたんです。ところが現在、NFLの収入は、当時の4倍近くに広がっています。『本国でそれだけ稼がれたら、NFL JAPANなんていらないんじゃないか』というのが僕らの悩みなんですけどね(笑)。
――日本とアメリカでは、スポーツ文化の「土壌」にどのような違いがあるのでしょうか。
町田 光 僕の理解として「文化として定着している」というのは、ある存在が、国や地域社会の多くの人々にとって大切なものだと認識されていて、それに日常的に何らかの形で関わることで自分たちの人生や社会が豊かで幸せになるものだと受け入れられている、という様なことだと思っています。その観点から見ると、アメリカのスポーツはまさにそうなっています。アメフトはもちろん、野球でもバスケでもサッカーでも非常に高いレベルでプレーしている世界があるかと思えば、下手だけどスポーツチームを作って楽しむ人が驚くほどたくさんいるんです。その層の厚さですよね。一方でスポーツには「見る」という側面もあります。それはプロスポーツだけではなく、たとえ子供のチームや地方のアマチュアチームであっても、それはそれで地元の人がちゃんと応援していて、試合当日になるとみんなで弁当を作って会場に行き、それが地域の重要なイベントになっていたりしている。様々なスポーツの話題が人々の共通の話題になっていて、そこでは人種も宗教も関係なくみんな一緒になってスポーツをやって、見て、楽しんで、応援する文化がありますよね。
――日本の場合はいかがでしょうか。
町田 光 トップレベルを目指す人は血のにじむような努力をしているけど、みんなが様々なレベルで楽しむ仕組みがあるかというと、あまりないですよね。サッカーを気楽にプレーできるスポーツとして始まったフットサルも、いつの間にかフットサルで日本一、世界一を目指す人のものになってしまった。だからスポーツは上手い人がやるだけで、苦手な人間を排除するような、そんな文化ですよね。「見る」という側面についても、例えばサッカー日本代表の公式戦だと視聴率が20%を超えることもあるし、オリンピックになるとものすごく盛り上がると思うんですよ。しかし、そういったイベントが終わるとスポーツなんて見なくなる。ただ一瞬の「盛り上がり」として消費しておしまい。そういう意味では、日本ではスポーツが文化として定着しているとは言えない感じがします。
――町田さんは「ファン・マネジメント」いう言葉を使われ、共著で本も出されていますがこれは具体的にどんなことを意味するのでしょうか。
町田 光 「顧客を創造し、ずっと大切にする」という、ビジネスでは当たり前のことですね。なぜそのような言い方をするかというと、日本のスポーツは「ファン(顧客)とはどのような存在か」という根源的な思考がないからなんです。スポーツをやっていたら自然に見に集まった人を「ファン」と呼んでいる。「観客動員」って言葉、これってただの「モノの数」扱いですよね。ファンは実はものすごくデリケートで多様なんです。もちろんサッカーなら、サッカーという競技を理解し、「観戦」することを目的にする「ファン」がその中心にいることは確かです。でも、特にこれは現在のプロ野球や地方のJクラブに顕著ですが、競技の観戦が目的ではなく、スポーツの試合という場を使って地元愛をベースにした地域のお祭に参加することを楽しむ人々が急拡大しています。スポーツテイストのファッションに身を包み、選手と共にボールを追いかけるような興奮を感じながらビールを飲んで、青空のもとで見知らぬ人とハイタッチして歓喜の叫びをあげる。皆が普段感じられない解放感や高揚感、幸せを感じているんです。そんな新たな「顧客」が大量に生まれています。これはスポーツの新たな、そして大量の「ファン」ですよ。この「新たな顧客層」をどうやって拡大し、継続的な顧客に取り込むか。そこに日本のスポーツビジネスの可能性が開かれていると思います。
――確かに古くはセレ女(※1)、最近はスー女(※2)など、いろいろなスポーツに今のお話のような新しい客層がどんどん増えているように感じます。何か背景があるのでしょうか。
町田 光 ちょっと理屈っぽい話をしますね。1980年頃まで、日本は資本主義社会にも関わらず、長い間国民の多くが中流階級であり、「まあまあ幸せ」と感じることのできた、ある意味で理想的な共同体社会だったんです。ところが、その後のグローバル化で、世界レベルの熾烈な競争が始まり、たったの20年で日本はすっかりその形を変えてしまいました。一言で言えば個人個人がバラバラになり、共同体が崩壊したのです。現代は人々の価値観の多様化が進み、それが個人の心の在り方や生き方を自由にした反面、社会的な視点から見ればいわゆるイケてる奴とイケてない奴、勝ち組・負け組や正規・非正規といった様々な「差」を作り出すんです。つまり日本はいつの間にか孤独や格差や絶望がどんどん広がる不安と高ストレスの社会になってしまったのです。これを哲学や社会学では「皆が共有できる大きな物語が失われた社会」と呼びます。すると、そこで人々は何を求めるようになるのかというと、人との繋がりや一体感であり、日常から解放される大きな感動であり、自分が生きていることを実感できる体験や経験の場です。ここまで言えば分かるでしょう。そう、ここにスポーツの役割があるんです。スポーツは沢山の人々に一体感と生きる事の喜びを感じさせる、非日常の感動体験を与えることができる装置なんです。スポーツが「大きな物語」になるんです。だから今、スポーツには新しい消費者が押し寄せているんです。いわばスポーツがなくてはいられない大衆が登場してきたのです。この「大衆」をしっかり自分のチームの顧客(ファン)にして、ずっと大切に繋ぎとめることがファンをマネジメントするという事です。
※1セレ女:「セレッソ大阪」の熱烈な女性サポーターを指す呼称
※2スー女:20代を中心とする若い世代の間で急増している、「相撲」にハマる女性を指す呼称

――Jリーグのファン・マネジメントについてはどう思われますか。
町田 光 日本のこれまでの考え方だと、サッカーは、サッカーの好きな人が見に来るものだ、というものでした。だから「良いサッカーの試合を人々に見せることが自分たちの仕事」と信じて疑わず、チームの優勝が最も大事なことで、優勝すれば全てが良くなると考えている。完全に間違いとは言えないですが、いくつかのチームのデータを見る限り、優勝した年の観客動員の伸び率は10%程度で、その翌年は元通りになるんです。スポーツビジネスにとって、勝利はボーナスであり、勝利を主たる価値にしてはいけない、という鉄則があるんですよ。J1リーグは18チームありますから、優勝する確率は18分の1。そんな可能性の低いことを最重要視するなんて、これほど危険なことはないですよ。でも、どうしてもそう考えてしまうんです。なぜならサッカーという競技にこだわりを持っている人達ばかりが経営しているからです。皮肉なことに、あまり野球というスポーツそのものに強い思い入れを持たない人たちが多く経営に携わっているプロ野球の方が、新たなスポーツ顧客の登場に積極的に対応できて、現在ほとんどのチームが観客を伸ばしているのとは対照的です。
――ファン・マネジメントの観点から、Jリーグで今後、スポーツビジネスの側面で成功する可能性のあるクラブはどこでしょうか。
町田 光 ファジアーノ岡山には注目しています。木村正明社長はビジネスの基本をよく理解している方だと思います。木村さんの講演で「スポーツファンの多様性」という事について、NFLがよく使う4層構造の図を使って説明されていて驚きました。また地域の自治体、政治家、商工会議所、アカデミー、町内会などを巻き込んでチームをその地域の共有財産、社会的装置、シンボルにしようとするなど、すごく本質的で的確な活動を展開されていると思います。
ビジネスの原則に立ち返って日本のスポーツビジネスを変える…元NFL JAPAN代表 町田氏が語る/前編
日本のスポーツビジネスの新たな可能性がすぐそこに有る…元NFL JAPAN代表 町田氏がその可能性を見極める/後編
シニア・ディレクター
町田光
大学卒業後、就職情報会社勤務を経て、1996年より16年間に渡り北米のプロアメリカンフットボール・リーグであるNFLの日本支社、「NFL JAPAN」の代表取締役を務める。
現在はNFL JAPAN リエゾンオフィスのシニア・アドバイザーの他、(公財)日本フラッグフットボール協会の専務理事、早稲田大学非常勤講師、早稲田大学スポーツナレッジ研究所招聘研究員、Jリーグマーケティング委員、笹川スポーツ財団企業スポーツ研究会座長の座長を務めるなど、経営学だけでなく、社会学・哲学的観点からスポーツと社会の関わりを研究している。
※著書・共著
・Jリーグの挑戦とNFLの軌跡 スポーツ文化の創造とブランド・マネジメント ベースボールマガジン社
・企業スポーツの現状と展望 笹川スポーツ財団(編)
・スポーツリテラシー 早稲田大学スポーツナレッジ研究所(編)
・ファン・マネジメント 早稲田大学スポーツナレッジ研究所(編)
他
サッカーキング・アカデミーにて、スポーツブランディングジャパン株式会社 町田氏の特別セミナーを実施!
By サッカーキング編集部
サッカー総合情報サイト

