リオ五輪初戦で5失点を喫した日本。堅守を誇ったはずのチームが守備崩壊した理由とは [写真]=兼子愼一郎
リオデジャネイロ・オリンピックは現地時間21日にマラカナンスタジアムでの閉会式が行われ、南米大陸で初めて開催された“スポーツの祭典”の幕が降ろされた。
テレビではハイライト番組が目白押しだが、残念ながら、その中に手倉森ジャパンの勇姿を見つけることはできない。日本が獲得したメダルの数は、過去最多となる41個に上る。感動的なシーンを振り返ろうとすれば、グループステージで敗れ去った団体競技に時間を割く余裕などないだろう。手倉森ジャパンの今夏の戦いを記憶していのは、サッカーファンを除けば、ほとんど皆無かもしれない。
ブラジルから帰国して一週間が経った。その間、多くの人から訊ねられたのは、次の質問に集約される。
なぜ初戦のナイジェリア戦で、あのような敗北を喫してしまったのか――。
■選手、指揮官が固執した『耐えて勝つ』

リオ五輪初戦に臨んだ日本代表先発メンバー [写真]=兼子愼一郎
堅守を武器にしていたチームが失点を繰り返して計5失点。守備崩壊に歯止めが効かなかった。0-5と完膚なきまでに叩きのめされたのなら諦めもつくが、失点はどれもチープなミスによるものばかり。しかも最終的に4-5と1点差まで追い上げたという事実が、「もったいない」という感情をより一層強くさせる。
日本が奪った3点目と4点目は、2-5と点差が大きく開いた後半半ば以降のものだった。ナイジェリアが油断したからこそ奪えたゴールだったという見方もできる。だが、サッカー協会の金銭問題が勃発したナイジェリア代表はキャンプ地のアメリカ・アトランタから出発することができず、試合会場のマナウスに入ったのは、キックオフ約7時間前のこと。コンディションが整わず、終盤を迎えて運動量がガクッと落ちたところを日本が突いたのも確かだろう。
狙いどおり、後半勝負の展開に持ち込めていれば――。
実際、手倉森誠監督と選手たちは“後半勝負”を狙っていた。だが、まさにそのゲームプランに、最初の落とし穴は潜んでいた。
「『耐えて勝つ』って、そればかり言い過ぎた面もあると思う」
ナイジェリア戦後のミックスゾーンで手倉森監督は、そう漏らした。「耐えて勝つ」という言葉は、今大会を迎えるにあたって指揮官が掲げていたテーマだ。本大会では「6割方、守勢に回るだろう」(手倉森監督)と予想する中、粘り強く戦いながらスキを突いて仕留める――それが、指揮官の思い描いた青写真だった。
もともとアジア最終予選から貫いてきたチームスタイルが「堅守速攻」だったこともあり、その考え方自体は間違ってはいない。問題だったのは、その“耐え方”だ。
ナイジェリア戦前日、指揮官は「ゲームの入り方はアグレッシブに、慎重に行って、最後、スキを突いて仕留められれば、という戦い方を描いている」と語った。この「アグレッシブに、慎重に」という言葉からは「攻撃的な守備で、先制点を与えない」という思惑がうかがえた。

遠藤は憧れのミケルとのマッチアップに「ビビらずにやります」と語っていた [写真]=兼子愼一郎
ところが「耐えて」を意識しすぎるあまり、「自陣でブロックを敷いて待つ守備だけになってしまった」とキャプテンの遠藤航(浦和レッズ)は振り返る。しかも、この試合では遠藤がアンカーを務める4-3-3が採用されていたため、従来の4-4-2で戦う場合よりもチームの重心が後ろに傾いていた。その結果、コンディション不良を視野に入れつつ、立ち上がりからトップギアで仕掛けてきたナイジェリアの攻撃を、守備陣が真っ向から受けることになってしまった。
4-3-3の採用理由について確認するタイミングを逸してしまったため、正確な狙いは定かではないが、「慎重にゲームに入りたい」こと、そして「ナイジェリアのトップ下、ジョン・オビ・ミケル(チェルシー)に遠藤をぶつけたい」という思いはあったはず。その一方で、指揮官に4-4-2ではなく4-3-3の採用を決断させた理由の一つとして考えられるのが、FW久保裕也(ヤングボーイズ/スイス)の招集断念だ。
もし、久保が合流できていれば、当初のプランどおりに久保と興梠慎三(浦和)を2トップに配した4-4-2で初戦に臨んでいたことが予想される。直前でヤングボーイズから久保の招集拒否に遭ったことも、「FWを一人削ってアンカーを置く」というプラン変更の要因だったのではないかと見る。

クラブ事情により大会直前で不参加となったFW久保裕也 [写真]=Bongarts/Getty Images)
「正直、(耐えるという言葉に)引っ張られたというか、その意識(耐える=引いて守る)になってしまっていた」
ナイジェリア戦翌日にそう振り返ったのは、川崎フロンターレのチームメートでもある大島僚太とインサイドハーフで並んで先発出場した原川力だった。
「でも、待つだけが耐えることじゃない。僕と僚太くんが相手のボランチにもっと行ってもよかった。相手にボールを持たせすぎてしまった。待っているだけじゃなく、取りに行く守備をもっとしなければならなかった」
強調された「耐えて勝つ」に引っ張られたことで、このチームがもともとコンセプトとして大事にしてきた「柔軟性と割り切り」が薄れてしまった。
オリンピックという大舞台、その初戦を迎えるにあたり、ただでさえ選手たちの心理状態はナイーブだったに違いない。これまで“あの手この手”を使って巧みに選手たちを「その気」にさせてきた指揮官が、この初戦に向けたマネジメントに関しては誤ってしまった。
■大会前の不運なケガ人続出が招いた誤算
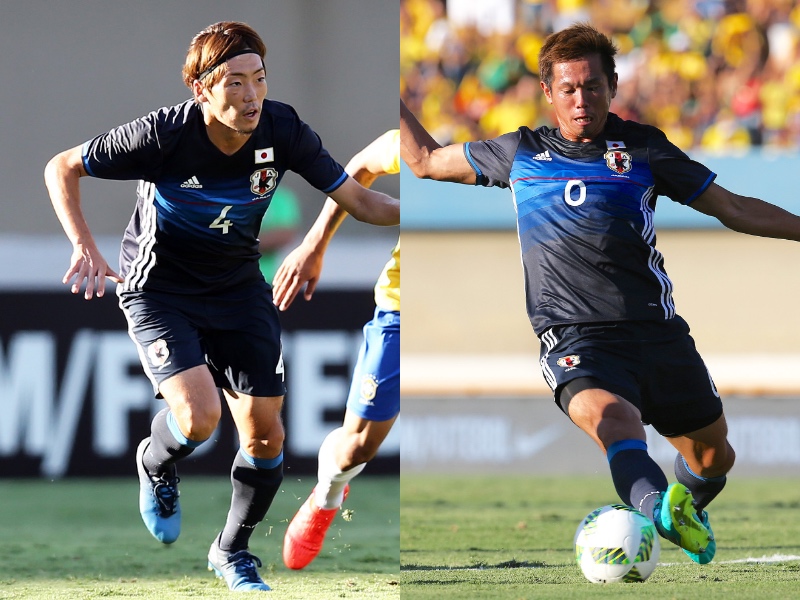
オーバーエイジ(OA)枠で招集されたDF藤春廣輝(左)とDF塩谷司(右)[写真]=Getty Images
では、オーバーエイジを二人加えたディフェンスラインの連係はどうだっただろうか。
ナイジェリア戦ではGKも含め、守備陣全員が失点に絡んでしまったが、守備崩壊の要因が、オーバーエイジとの連係不足そのものにあったとは言い切れない。連係うんぬんの前に、個人によるミスが目立ったからだ。
1失点目は中島翔哉(FC東京)とともに2対1で対応しながら、オーバーエイジの藤春廣輝(ガンバ大阪)が簡単にかわされてシュートを打たれ、GK櫛引政敏(鹿島アントラーズ)が弾いたところを詰められてしまった。2失点目は室屋成(FC東京)がクロスの目測を誤ってシュートを叩きこまれた。3失点目はオーバーエイジの塩谷司(サンフレッチェ広島)がいったんマイボールに収めながら相手に奪われ、最後は植田直通(鹿島アントラーズ)のクリアが相手に渡ってしまった。4失点目も塩谷と室屋が奪ったボールを譲り合ってしまい、ペナルティエリア内への進入を許した。5失点目は大島のパスが奪われ、GK櫛引のクリアミス(あるいは判断ミス)によって生まれたものだった。
試合後、塩谷や藤春が「思っていた以上に足が伸びてくる」と振り返ったように、これまでほとんど経験したことのないアフリカ勢特有の身体能力に対応できなかったという影響はあるが、いずれも一人ひとりの守備力が問われる失点だった。

ナイジェリアOAのミケルと競り合う藤春(左)[写真]=Getty Images
もちろん、オーバーエイジとの融合の遅れがディフェンスラインの心理面に影響を及ぼした点は否めない。ディフェンスライン4人中二人がオーバーエイジという状態で、彼らとの連係をようやく図ることができたのは、大会直前のアラカジュ合宿からだった。とはいえ、セルジッペ(ブラジル4部)との練習試合、ブラジル代表との親善試合をこなしたが、2試合ともメンバーを入れ替えて戦ったため、計180分間、連係を磨くことに充てられたわけではない。長く戦ってきたメンバーによって「やるべきことはやった」という状態で開幕を迎えた最終予選とは異なり、「うまくいくかどうか」という心理状態でナイジェリアとの初戦を迎えることになってしまったのは確かだろう。
オーバーエイジの人選に関して、もともと手倉森監督は、本田圭佑(ミラン/イタリア)や岡崎慎司(レスター/イングランド)、長友佑都(インテル/イタリア)といったフル代表の主力を望んでいたと言われているが、ヨーロッパの各国リーグが8月に開幕すること、フル代表の主力は9月から始まるロシア・ワールドカップのアジア最終予選に専念させるため、断念せざるを得なかったとされている。
それゆえ、対象は国内組に切り替えられたが、考慮しなければならなかったのが、手倉森ジャパンの候補メンバーにケガ人が続出したことだった。
選手たちは昨年12月、Jリーグのシーズンを終えた直後にカタール・UAE遠征を行い、年末には石垣島合宿を敢行(一部選手はクラブワールドカップや天皇杯に出場したため不参加)。そして1月からカタールでのアジア最終予選に臨んだ。ここでは6戦全勝という最高の結果でアジアの頂点に駆け上がったが、韓国との決勝が行われたのは1月30日のこと。最終予選から戻った選手たちはシーズン終了後からオフをほとんど取れないまま、クラブのキャンプに合流し、新シーズンへと突入した。こうして疲労を抱えたままの選手たちは、次々と故障してしまう。

大会前の負傷もありメンバーから外れた(左から)松原、奈良、山中 [写真]=Getty Images
DF室屋 成 左足ジョーンズ骨折(全治約3カ月)
FW鈴木武蔵 左大腿四頭筋肉離れ(全治約3カ月)
DF松原 健 右ひざ外側半月板損傷(全治約3カ月)
MF大島僚太 右足首腓骨筋腱炎悪化
FW浅野拓磨 右腸腰筋損傷(全治約3週間)
MF中島翔哉 右ひざ内側側副靭帯損傷(全治約5〜6週間)
DF奈良竜樹 左足脛骨折(全治約4カ月)
DF山中亮輔 右大腿二頭筋肉離れ(全治約3週間)
DF岩波拓也 左ひざ内側側副靭帯(全治約6週間)
とりわけディフェンス陣に負傷者が続出した。左利きの左サイドバックである山中の代わりとして、同じく左利きのサイドバックとしてフル代表にも選ばれている藤春が選出されたのは当然の流れとも言える。また、センターバックの岩波拓也(ヴィッセル神戸)、右サイドバックの松原健(アルビレックス新潟)と室屋のうち、誰が間に合って誰が間に合わないのか、ギリギリまで判断がつかなかったことを考えれば、センターバックとサイドバックをこなせるフル代表経験者の塩谷が選出されたのは、自然な流れだ。
この時点でオーバーエイジは“強力な助っ人”というよりも、まさに「穴を埋めるための補強」だった。指揮官も、藤春と塩谷に世界大会の経験がないことは承知の上で、「U-23世代とともに一緒に成長していって、ロシア・ワールドカップのピッチに立ってほしい」と語っている。
興梠も含むオーバーエイジの3人は、強烈なリーダーシップを備えていたわけではなかったが、だからこそチームにはスムーズに溶け込むことができた。年下の選手たちが話しかけるのを遠慮するようなこともなく、チームの雰囲気が変わることもなかった。藤春に至っては年下の選手たちからイジられ、笑いを生んでいた。

OA枠の興梠慎三(右)は3試合全てに先発出場した [写真]=Getty Images
オーバーエイジと言って思い出されるのは、2004年のアテネ・オリンピックだ。山本昌邦監督に率いられたチームはオーバーエイジとして小野伸二(コンサドーレ札幌)と曽ヶ端準(鹿島アントラーズ)を迎え入れた。小野は当時、オランダのフェイエノールトに所属し、ジーコが指揮を執るフル代表の中心選手でもあった。この件に関して当時のメンバーだった今野泰幸(G大阪)は「オーバーエイジの選手のオーラがすごすぎて、ついていく感じになってしまった」と振り返る。それだけに、もし本田や長友を招集できていたとしても、純粋に戦力がプラスになったかどうかは分からない。日本の場合、オーバーエイジの人選は難しい。
リオでは結果的にオーバーエイジの選手によるミスが響いたが、選考における条件や負傷者の状況を考えれば、興梠、塩谷、藤春という人選が誤りだったとは言えない。むしろ、状況を難しくしたのは、オーバーエイジの合流時期だろう。5月のトゥーロン国際大会でメンバー選考を終わらせ、6月末の長野合宿と29日の南アフリカ戦でオーバーエイジを合流させていれば、開幕直前まで融合に時間と神経を割かなければならない状況は避けられた。ところがトゥーロン国際大会で岩波までが負傷する状況に陥り、南アフリカ戦をケガ明けの選手たちの回復状態を確認する場、当落線上の選手たちを最終確認する場にせざるを得なくなってしまったのは、手倉森監督にとって誤算だったに違いない。
■“繊細さ”を欠いたGK起用法

正GKの座を争った櫛引政敏(左)と中村航輔(右)[写真]=Getty Images
ナイジェリア戦では鹿島で出場機会を得られていないGK櫛引が先発起用された。所属クラブで常時、試合に出ているGK中村航輔(柏レイソル)がスタメンだったならば5失点も喫しなかったのではないか、という見方も散見される。
確かに櫛引は、何度かキックの処理に不安をのぞかせ、飛び出しからのクリアミスで5点目を与えてしまった。試合勘のなさを指摘されても仕方がない。とはいえ、彼はシュートストップに定評があり、ビッグセーブを連発することがある一方で、足下の技術や飛び出しの拙さは、常時試合に出ていた清水エスパルス時代やアジア最終予選でものぞかせていた。ナイジェリア戦でのパフォーマンスは試合勘の欠如というより、もともと抱えていた課題が出たものだろう。櫛引は今季加入した鹿島では試合に出られていないが、清水時代の2013年にはJ1で20試合に出場し、この世代でいち早く出場機会をつかんでいる。2014年1月にチームが立ち上げられてからは、手倉森ジャパンの正GKをずっと担ってきた。
一方、中村は昨季期限付き移籍したアビスパ福岡で正GKの座をつかみ、今季から復帰した柏でも試合に出場し続けている。中村にとって痛かったのは、昨年12月の石垣島合宿で負傷し、アジア最終予選のメンバーから外れてしまったことだろう。確かに現状でのゲーム経験は中村が櫛引をしのいでいるが、このチームでの実績は櫛引のほうが圧倒的にあるのだ。しかも今大会では最終ライン4人中二人もオーバーエイジを起用したことで連係面に不安を残していた。GKはこれまでこのチームのゴールを守り、植田や室屋との連係がすでに築かれている櫛引を送り出した手倉森監督の判断はうなずける。
疑問があるのは、初戦を迎えるまでの両GKの起用法だ。
アジア最終予選当時、手倉森監督は「強いチームはGKの序列がはっきりしているものだ」と明言。ターンオーバー制を用いたフィールドプレーヤーとは異なり、消化試合となったサウジアラビア戦を除く5試合でGK櫛引を先発起用した。
ところが今回、セルジッペとの練習試合では櫛引が先発し、中村が後半から出場。ブラジルとの親善試合では中村が先発し、櫛引が後半から出場と、出場時間は全くのイーブン。むしろ、ブラジル戦に先発した中村が正GKという印象すら抱かせた。もし櫛引に正GKを任せるつもりだったなら、ナイジェリア戦前の2試合のテストマッチではいずれも櫛引を先発させ、櫛引が正GKだということを明確にするべきだったのではないか。ここには競争意識を高めたいという意図があったのかもしれないが、孤独な戦いを強いられるGKに、開幕直前までポジションを競わせ、神経をすり減らさせてもプラスになることはほとんどない。
コロンビアとの2戦目で中村を先発起用した際、手倉森監督は櫛引に「自信を回復させる場を必ず与える」と伝えている。グループステージで敗退したため、結果的に櫛引がピッチに立つ機会はなかったが、決勝トーナメントに進出していれば、櫛引が再びスタメンに名を連ねていたかもしれない。このエピソードは指揮官の櫛引への信頼の高さを示しているが、一方で、選手への心理マネジメントを得意とする監督としてのモチベーターぶりも表している。そうした“気遣いの人”だからこそ、ビッグトーナメントを迎える寸前の正GKに対する扱いについて、もう少し繊細になるべきだった。

まさかの打ち合いに手倉森監督も苦い顔を浮かべた [写真]=兼子愼一郎
■避けられなかった守備崩壊
ナイジェリアの攻撃陣に対し、日本の守備陣が一対一の対応で劣っていたのは間違いない。しかし、それ以上にU-20ワールドカップへの出場を逃し、国際大会で真剣勝負に臨んだ経験がほとんどなかったことで、世界大会の雰囲気や世界大会の初戦への入り方をこれまで味わって来られなかった影響も大きい。ナイジェリア戦翌日、室屋は「開始早々に失点して、自分のミスもあって失点を重ねて慌てたというか、責任をすごく感じて引きずってしまった」と明かした。スウェーデンとの第3戦を終えた後、塩谷は「(オーバーエイジとしてのプレッシャーは)やっぱりありました。意識しないようにと思っても、どこかで意識してしまった……。初戦もそれで気負いすぎたのかなと思います」と胸の内を吐露している。
必要以上に意識しすぎた「耐えて勝つ」のゲームプラン、重心を後ろに重くした4-3-3の採用、開始早々のゲームプラン崩壊、合流が遅れたオーバーエイジとの連係不安、世界大会での経験不足、初戦ゆえのナイーブな心境、オーバーエイジの選手たちが必要以上に抱えていた責任感……。こうした要素が絡み合い、ナイジェリア戦での守備崩壊は起こるべくして起こってしまったのだ。この後、手倉森ジャパンは敗戦のショックを感じさせず、反発力を発揮してチームの集大成を感じさせる戦いをしっかりと披露した。だからこそナイジェリアとの初戦で見せたつまずきが、あまりにもったいなかった。
『【手倉森ジャパン徹底検証/後編】リオ五輪で見えた手応えと東京五輪への提言』に続く
文=飯尾篤史
